この記事で紹介する5つの力
エンジニア、初心~中級までに意識するべき事をざっと書き出してみます。
タスクこなすのに夢中になりがちですけど、以下の視点が後々重要になってきます。自分自身が若手時代に苦労したこと、現場で火消した経験を踏まえて、今だからこそ伝えたいことをまとめました。
🗓️ 1. スケジュール管理の鉄則
- 「今日やること」を毎朝明確にする(ToDoリスト+優先度)
- 締め切り=相手の期待値と捉える(納期遵守は信頼構築)
- WBSの粒度を自分で調整できるようになる(自律的な進行管理)
- 見積もり時間は×1.5で仮置きする(工数見積もりの精度を高める鉄則)
🧠 2. 段取り力の磨き方
- 目的→手段→手順の順で考える癖をつける
- 「誰が・いつ・何を・どう使うか」を先に整理(スコープ範囲の明確化)
NG例:「とりあえず検証始めたら迷子」
→ 目的や評価基準を決めずに手順から入ると、時間だけ消費して成果ゼロになる💡 テスト環境は「遊び場」ではなく「仮説検証の場」 - 新人のうちは目的を先に言語化できないことが多いので、必ず「何を確かめたいか」「どうなったらOKか」を決めることが重要
- レビューや確認のタイミングを事前に設計する
(レビュアー(誰が確認するか)、レビューイ(誰が直すか)、再レビュー、レビュー修正時間をWBSに含める)
🔍 3. 優先度の判断軸
- 緊急度 × 重要度で4象限に分けて考える
- 「契約条件に関わるか?」を優先度判断の軸に加える
- 「現場が燃えるかどうか?」をリスク視点で補完する
- 例:自分にとって優先度低いものでも、顧客や上司にとっては最優先になることがある。分からなければ必ず相談!
📚 4. ナレッジ蓄積と標準化意識
- 作業後に「再利用できるか?」を自問する
- 命名規則・フォルダ構成・手順書の整備を意識
- 若手でも使える資料=自分の成長の証
🧩 5. コミュニケーションと報連相
- 「報告=安心材料」「連絡=調整材料」「相談=信頼材料」
- SlackやTeamsでの文面も「目的→背景→提案」の順で構成
- 上司や先輩の「判断材料」を意識して情報を出す
- 例:コミュニケーションに「記録」があると助かる
- SlackやTeamsで伝えるだけでなく「議事録・タスク一覧に反映」までしておくと、後で火消し時に助かる
⏳ レビュー設計におけるバッファーの考え方
🔁 再レビューの前提を作る
- 初回レビュー=指摘抽出フェーズと割り切る
- WBSに「再レビュー」という工程を明記する(「レビュー完了」ではなく「レビュー通過」)
- 指摘対応の粒度に応じた再レビュー方式(軽微ならチャット確認、重めなら再レビュー会)
🛠️ 指摘事項の修正時間を確保する
- 「指摘→即修正→即再レビュー」は非現実的。修正者の理解・調整・反映に時間が必要
- 修正時間=品質担保のための投資と位置づける
- 修正者が“納得して直せる”時間を確保する(属人化排除にもつながる)
📅 バッファーの設計ポイント
- 全体工数の1~2割をバッファとして確保する(レビュー・修正・追加依頼の吸収)
- クリティカルパス上のタスクに厚めのバッファを置く(全体遅延のリスク回避)
- レビュー・承認フローには必ずバッファを入れる(依頼者の予定に依存するため遅延しやすい)
- バッファは「見せる/見せない」を使い分ける(顧客向けスケジュールとチーム内管理を分ける)
🧩 補足:レビュー設計の視点
- 成果物が要件通りか、スコープ範囲内かを明確にする
→ 契約条件との整合性をレビュー観点に含め、契約外作業の混入や追加対応のリスクを未然に防ぐ - 指摘の背景を共有し、育成と納得感を両立する
→ レビューシートに「指摘事項」「修正方針」「理由」を明記し、若手が“なぜ直すのか”を理解できるようにする - ナレッジ蓄積のために、指摘履歴を残す仕組みを設ける
→ 属人化排除・再利用性向上に貢献 - 若手側の視点:「レビューは“試験”じゃなくて“対話”。指摘が多くても改善のチャンスと捉えることが大事」
- リーダー側の視点(補足):「レビューする側も、心理的ハードルを下げる工夫が必要。粗探しではなく改善提案として伝えることで、安心して受け止めてもらえる」
- レビューで指摘事項が多いと最初は落ち込むが、より良くするための機会と捉えることが重要
- レビューは「試験」ではなく「対話」
- 指摘=ダメ出しではなく「品質改善の提案」
- 安心してレビューを受けられる空気を作るのもリーダーの役割
🧩 まとめ:現場を燃やさないための“5つの力”を若手のうちに
若手時代は「タスクをこなすこと」に集中しがちですが、
本当に現場を支えるのは、段取り・優先度・レビュー設計・ナレッジ蓄積・報連相といった“現場力”です。
これらを意識することで、
✅ 自分の成長が加速し、
✅ チームの信頼が高まり、
✅ 現場が燃えずに回るようになります。
「レビューは試験ではなく対話」——この言葉を胸に、安心して改善提案を受け止められる文化を一緒に作っていきましょう。
🧩 SES構造の落とし穴と対策
「違う会社の人が教えてくれる」と思わない方がいい。
- SESでは、教育責任が曖昧になりがち
- 上位会社の人は「教える義務がない」し、「教えると責任が発生する」と思っていることもある
- だからこそ、最初は“3人程度でまとまって現場に入れる会社”を選ぶのが安全策
→ 相談できる仲間がいるだけで、現場の心理的安全性は大きく変わる
→ 教育体制がない現場では「ナレッジ蓄積」「標準化」「レビュー設計」が命綱になる
近いうちにSES、SIERについても記事にしたいと思います。
💬 コメントや質問があれば、お気軽にどうぞ!
👉キャリアの始まりはこちらからどうぞ!
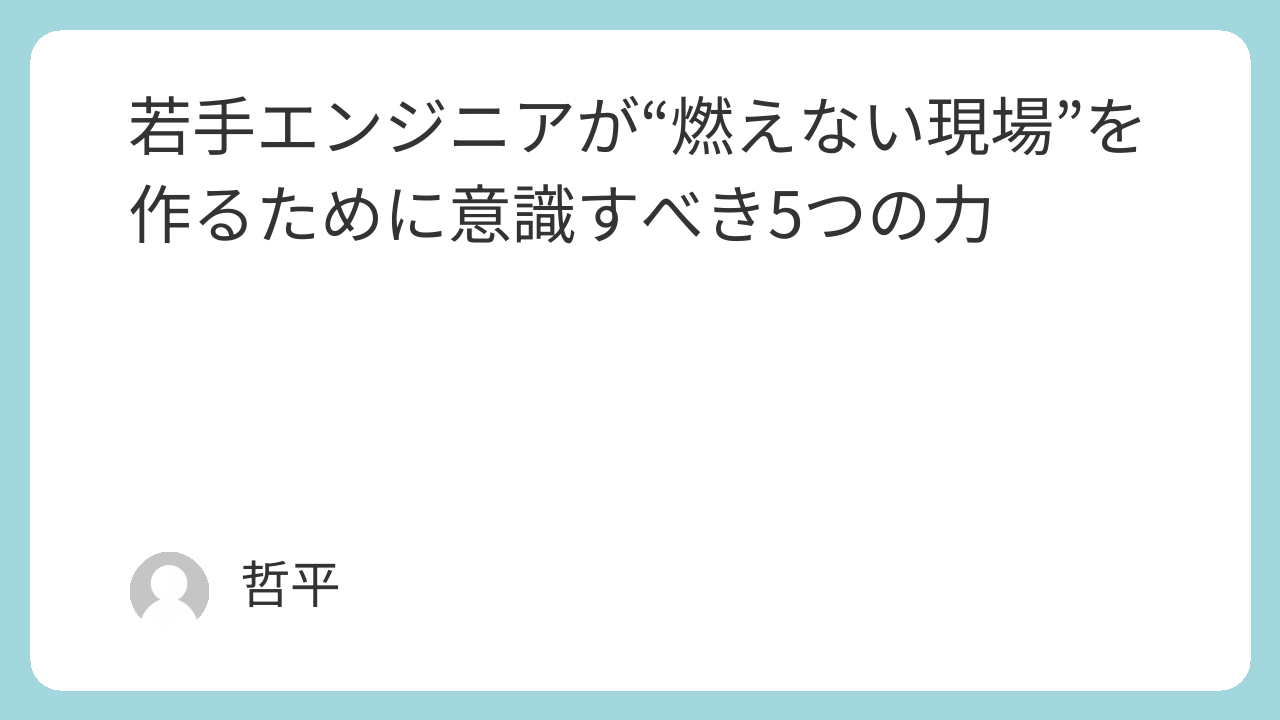
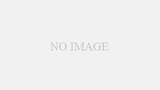
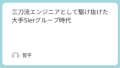
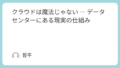
コメント